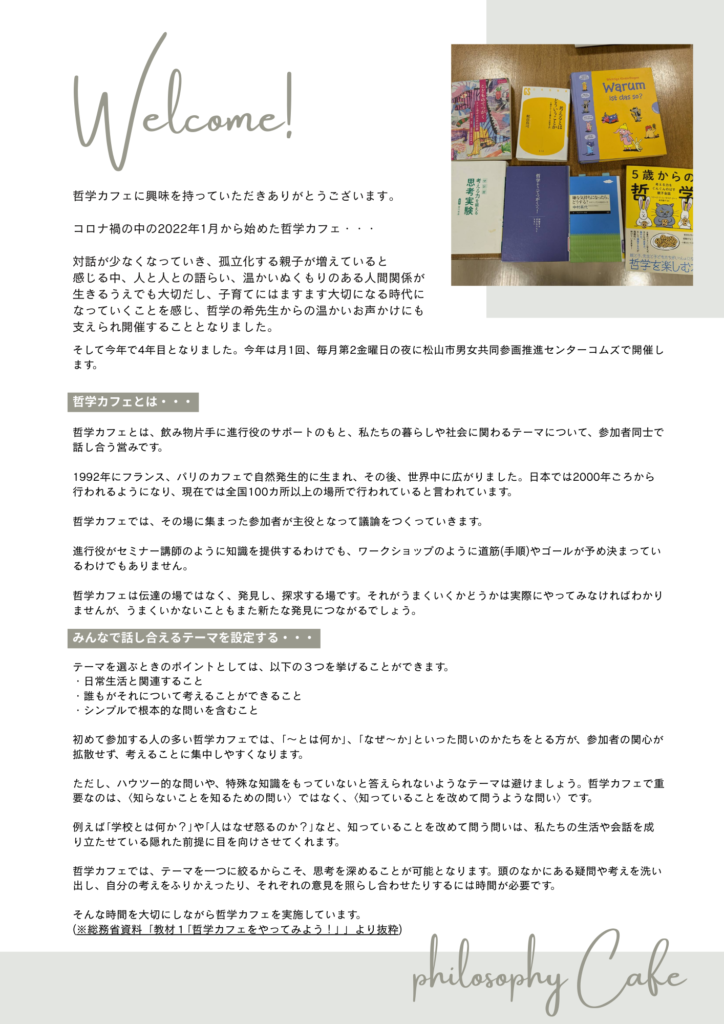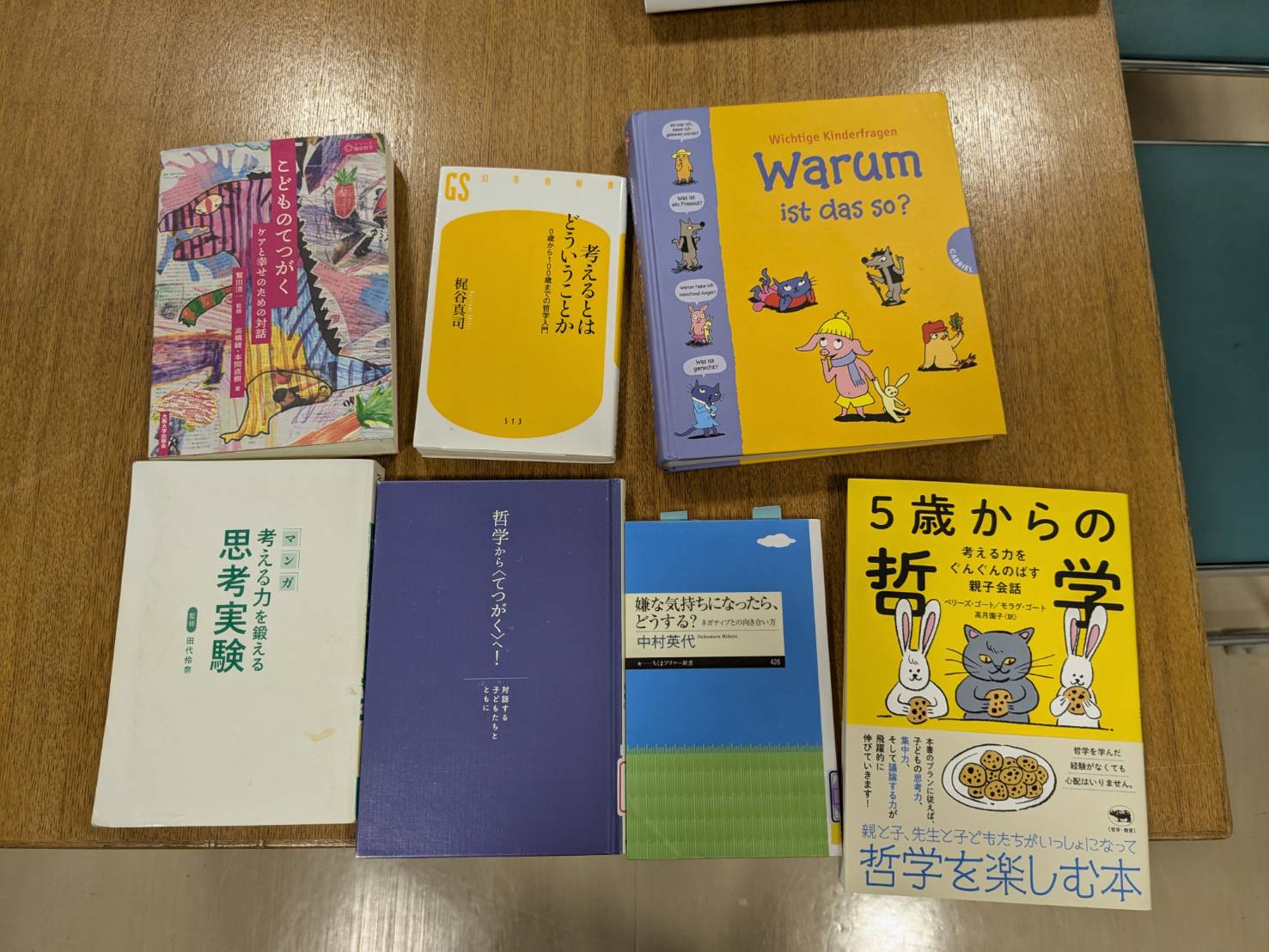コロナ禍の中の2022年1月から始めた哲学カフェ・・・
対話が少なくなっていき、孤立化する親子が増えていると感じる中・・・
人と人との語らい、温かいぬくもりのある人間関係が生きるうえでも大切だし、子育てにはますます大切になる時代となっていくことを感じ、哲学の希先生からの温かいお声かけにも支えられ開催することとなりました。
そして今年で4年目となりました。
今年は月1回、毎月第2金曜日(変更する場合あり)の夜に松山市男女共同参画推進センターコムズで開催しますので、皆様の参加をお待ちしております。
2025年度の哲学カフェのテーマ
| 4/11㊎ | 18:30~20:30 | 「痛み」を哲学する |
| 5/9㊎ | 18:30~20:30 | 「対話」を哲学する |
| 6/13㊎ | 18:30~20:30 | 「学び」を哲学する① |
| 7/11㊎ | 18:30~20:30 | 「学び」を哲学する② |
| 8/8㊎ | 18:30~20:30 | 「好き」と「嫌い」 |
| 9/12㊎ | 18:30~20:30 | 「うそ」と「本当」 |
| 10/10㊎ | 18:30~20:30 | 「ひま」を哲学する |
| 11/14㊎ | 18:30~20:30 | 「幸せ」と「不幸せ」 |
| 12/12㊎ | 18:30~20:30 | 「恐怖」と「不安」 |
| 1/9㊎ | 18:30~20:30 | 「お金」について |
| 2/6㊎ | 18:30~20:30 | 「友達」ってだれ? |
| 3/13㊎ | 18:30~20:30 | 生まれることと死ぬこと |
※2月は当初は2月13日㈮に開催予定でしたが、開催場所が使用できない関係で日程を2月6日㈮に変更しています。
開催場所:松山市男女共同参画推進センターCOMS
愛媛県松山市三番町6丁目4番地20
参 加 費:1000円 学生さん500円 (お菓子・飲み物付き)
対 象 者:哲学に興味があれば年齢は問いません。
≪申込方法&問合せ≫
下記申込フォームより申込ください。
NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場
https://asobiba-matuyama.org/
℡ 080-8902-9627(山本)
1 哲学カフェとは?
哲学カフェとは、飲み物⽚⼿に進⾏役のサポートのもと、私たちの暮らしや社会に関わるテーマについて、参加者同⼠で話し合う営みです。
1992年にフランス、パリのカフェで⾃然発⽣的に⽣まれ、その後、世界中に広がりました。⽇本では2000年ごろから⾏われるようになり、現在では全国100カ所以上の場所で⾏われて
いると⾔われています。
哲学カフェでは、その場に集まった参加者が主役となって議論をつくっていきます。
進⾏役がセミナー講師のように知識を提供するわけでも、ワークショップのように道筋(⼿順)やゴールが予め決まっているわけでもありません。
哲学カフェは伝達の場ではなく、発⾒し、探求する場です。それがうまくいくかどうかは実際にやってみなければわかりませんが、うまくいかないこともまた新たな発⾒につながるでしょう。
2 哲学カフェの構成要素
哲学カフェに、決まった定義や⽅法はありません。主催者や進⾏役によって、徹底的に討論する、ふだんのおしゃべりのようにフランクに話す、複数の論点や話題を⾏ったり来たりする、⼀つの論点を深く掘り下げる‥‥‥など雰囲気も進め⽅も様々です。
とはいえ、開催のために不可⽋な共通の要素として、以下を挙げることができる
でしょう。これらの構成要素には、それぞれ様々な選択肢があります。
(1)落ち着いて話せる場所と時間
喫茶店、地域のコミュニティスペース、図書館や美術館に併設されたカフェテリアなど、基本的に誰もが⾃由に出⼊り可能で、飲⾷が許されており、堅苦しくなく落ち着いて話し合える場所が良いでしょう。
哲学カフェでは参加者の⾃発性を重視するので、できれば、参加者の都合や関⼼によって途中⼊退場が可能な場所が望ましいです。
時間は、週末など休みの⽇に2〜3時間⾏われるのが⼀般的です。3時間の場合は疲れるので、途中で10〜15分ほど休憩をはさむと良いでしょう。
また、発⾔者が偏っている場合も、休憩をはさむと他の⼈が発⾔しやすくなり効果的です。
平⽇夜に開く場合は、会社帰りに⽴ち寄りやすいよう、ビジネス街の近くやアクセスの良いところを選ぶと⼈が集まりやすくなります。
(2)みんなで話し合えるテーマ
まず、テーマの決め⽅ですが、あらかじめ主催者や進⾏役によって決められたテーマの下に参加者が集まる場合と、当⽇集まった参加者にテーマを提案してもらって決める場合とがあります。定期的に哲学カフェが⾏われ、テーマに関わらず参加者が集まるような場合は、その場に集まった⼈たちが即興でテーマを設定することもできます。
ただ、テーマを⾒て関⼼をもつ⼈も多いので、新しい参加者に来てほしい場合は、進⾏役があらかじめテーマを設定し、事前に告知しておくことをおすすめします。
テーマを選ぶときのポイントとしては、以下の3つを挙げることができます。
・⽇常⽣活と関連すること
・誰もがそれについて考えることができること
・シンプルで根本的な問いを含むこと
初めて参加する⼈の多い哲学カフェでは、「〜とは何か」、「なぜ〜か」といった問いのかたちをとる⽅が、参加者の関⼼が拡散せず、考えることに集中しやすくなります。
ただし、ハウツー的な問いや、特殊な知識をもっていないと答えられないようなテーマは避けましょう。哲学カフェで重要なのは、〈知らないことを知るための問い〉ではなく、〈知っていることを改めて問うような問い〉です。
例えば「学校とは何か?」や「⼈はなぜ怒るのか?」など、知っていることを改めて問う問いは、私たちの⽣活や会話を成り⽴たせている隠れた前提に⽬を向けさせてくれます。
哲学カフェを体験したことがない⼈のなかには、「2〜3時間もあるのにたった⼀つのテーマで間が持つのか」、「⼀度に複数のテーマを取り上げたい」と思う⼈がいるかもしれません。
しかし、哲学カフェでは、テーマを⼀つに絞るからこそ、思考を深めることが可能となります。頭のなかにある疑問や考えを洗い出し、⾃分の考えをふりかえったり、それぞれの意⾒を照らし合わせたりするには時間が必要です。
テーマを選ぶときは、2〜3時間かけてじっくり考えたいと思えるテーマを選びましょう。
(3)対話をサポートする進⾏役
進⾏役をするのに、哲学者や哲学史に関する知識は必要ありません。必要なのは、相⼿の話を聞きながら慌てずゆっくり考えるという⼼構えです。
進⾏のやり⽅に正解はなく、参加者やテーマ、場所、進⾏役の個性などによって様々です。
例えば、ひとりひとりの発⾔者と進⾏役で問答を繰り広げる「問答型」。
このタイプの進⾏役は、発⾔者それぞれの意⾒を⼀つ⼀つ吟味し、疑問を投げかけたり、ときには反論したりします。また、いわゆる「ファシリテーター」役に徹する進⾏役もいます。
このタイプの進⾏役は、⾃分の意⾒は表明せず、参加者の発⾔を助けたり、発⾔の意味が明確か他の参加者に確認したり、複数の意⾒の関連を確認したりと、参加者同⼠の対話を促進させることを重視します。さらに、他の参加者と同じように対話に参加しながら議論を活性化させる、「参加型」の進⾏役もいます。
フランスでは、進⾏役は「アニメーター(animateur)」と呼ばれています。これは、「〜を盛り上げる」、「〜を活気づける」、「〜に魂を吹き込む」といった意味を持つanimerという動詞から派⽣した⾔葉です。
ともに考え対話を活性化させるために何ができるのか⾃分⾃⾝で考えるこ、そして何より進⾏役⾃⾝が⽬の前で繰り広げられる対話を楽しむことが⼤切です。
(4)テーマに関⼼のある参加者
もちろん、参加者にも哲学者や哲学史の知識は不要です。テーマに関⼼があればどなたでも参加可能です。
哲学カフェにおいて、参加者は、主催者が提供するプログラムの「受け⼿」としてそこにいるというより、議論に参加することによって共に場をつくっていく「担い⼿」として存在します。
参加者がいなければ企画が成⽴しないばかりか、同じテーマや素材でも、参加者の関わり⽅によってその場で論じられる内容は⼤きく変わってきます。
⼀度も発⾔せず他の⼈の発⾔に⽿を傾ける参加者も例外ではありません。
発⾔せずとも、その態度や反応によって発⾔者の発⾔に影響を与えることから、彼らもまた場の「担い⼿」であるといえます。
哲学カフェは、3⼈でも100⼈でもできますが、決まった時間で発⾔できる⼈数は限られます。
「今⽇はじっくり考えることができたな」と感じる対話をふりかえると、どんなに参加者が多くとも、発⾔者数は⾃然と12⼈程度に収まっていることが多いようです。
あまり多くの⼈が意⾒を述べると、話題や論点が拡散してしまい、せっかく浮かび上がってきた論点を⼗分に吟味できないまま時間が終わってしまいます。
主催者や進⾏役が「なるべく多くの⼈の声を聞きたい」という場合はそれもかまいませんが、話すだけでなく「ともに考える」という体験をしたければ、発⾔者数にこだわるのはやめましょう。
重要な意⾒や仮説を提⽰してくれた⼈が他の⼈より多く発⾔するのは、⾃然なことです。
適切な参加者数は、会場の広さや席数によっても変わってきますが、全員が発⾔し、かつ内容も充実させたいという場合は、定員を10〜15⼈に設定すると良いでしょう。
12⼈までなら、テーマについて全員が⾃分の意⾒を述べることができます。
15⼈の場合は、全員が意⾒を述べるのは難しいので、最後に5〜10分程度、感想を語り合う時間を設け、まだ話していない⼈に感想を述べてもらいましょう。
※総務省資料「教材1「哲学カフェをやってみよう!」 」より抜粋