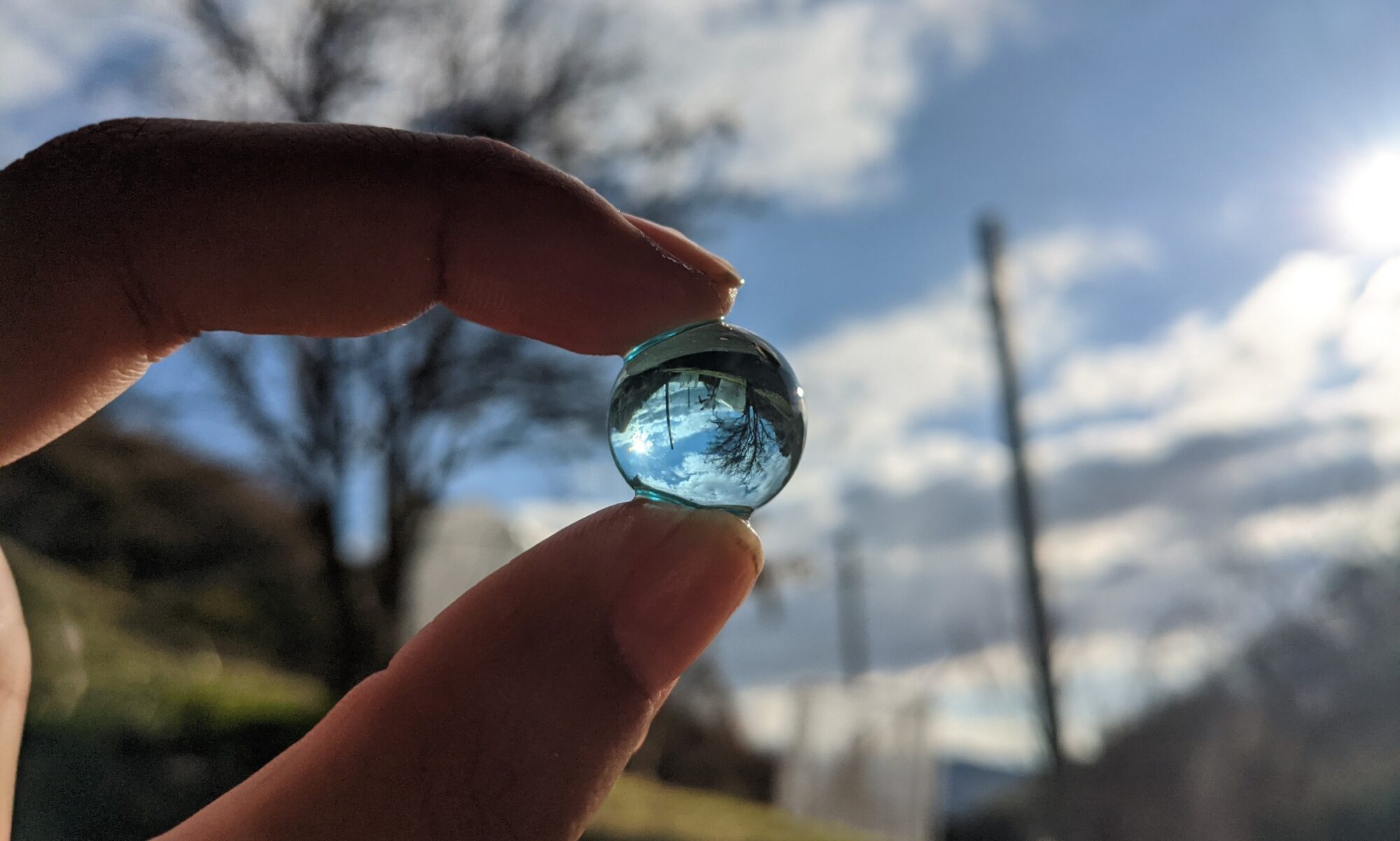- 自然の中で遊ぶ経験は自分自身の「幸福感」を育てること
- 外遊びが社会を開く
- 人工化する子どもたち
「虫眼」て言う言葉があるんですがご存知ですか?
この言葉は解剖学者 養老孟司さんと、アニメーション作家 宮崎駿さんとの3度にわたる対談集が本になった「虫眼とアニ眼」で私も知ったんですが、日頃自然の中を歩くことが多くなると、今まで見えていなかった虫だったり花だったが見えてくるようになり、その虫の小さな動きだったり、花や木々による季節の変化だったりを見つけて感動できるセンスのことで、そんな自然の恵みに感謝できる感覚、それ事態を「幸せ」なことと捉えることのできる人、それが「虫眼」の人だと私は思ってこの本を読みました。
私も最近少しだけ、その感覚がわかるようになった気がします。
遊び場の中で、見たことのない虫を発見してみたり、きのこやクワガタ、アリンコまで、今までいたであろうけど、自分では見つけることができなかった虫や植物を発見できる喜び、それから季節の変化を感じること、夕日を山の上から眺めながら「幸せ」を感じたり…
当たり前が当たり前ではなく「ありがたい」って思えて心が暖かくなって、「幸福感」に繋がっていく感覚・・・
私を含め、今の人はそうした自然との関わりが少なくなってるから、目の前の自然に「幸福感」を感じることが少なくなってしまっているように思います。
それでも、小さな子どもたちは「遊び」を通じて、そんな感覚をすぐつかむことができます。
大きくなればなるほど自然の煩わしさが「めんどくさい!」と言う感覚になってしまい、エアコンの効いた部屋でゲームなどをすることで、満足感を得ようとします。それは子どもたちだけの問題ではなく、大人の後ろ姿を見ながら育つ子どもたちにとっては、至極当然のことだったりします。
そんな子どもたちも一度山へ出かけてみると、汗かいて疲れることは確かなんだけど、のびのびと遊び、走り、虫を捕まえ、川の水の冷たさに癒され、山を流れる穏やかな風を感じ、鳥のさえずり、虫の鳴き声を聞いて、山を降りる頃にはエアコンの効いた娯楽施設の帰りに感じるものとは違う、すがすがしさを感じることができるかもしれません。
この感覚は人それぞれで、山に登る時の気持ちや、子どもとの関係、スタッフとの関わりなど、すべての人がそのことを感じることはないかもしれないけど、私たちとしては少しでも多くの人がそんな「幸福感」を感じてくれることを願って活動しています。
毎日の暮らしの中に「幸せ」は潜んでいるけど、それを毎日見つけられる人と見つけられない人がいて、尚且つ「不幸」を毎日探しているような悲しい人も今は多いように思います。そして、お金を出して娯楽施設に行くとか、豪華な宝石や服を購入することにしか、「幸せ」を感じられない人も増えているような気がします。
自然のある場所に行くだけで、もしかしたら「素敵」て思う人は「幸せ探しの上手な人」で、「つまんない」て思う人は「幸せ探しの下手な人」なのかもしれません。
そう考えると、子どもの頃に幸せ探しが上手になるために、自然の中で、楽しむ自分自身を見つけることは、子どもたちの未来の「幸せ」に繋がっているような気もするのです。
そうはいっても、自分自身も子どもの頃は毎週親に連れられて山に出かけていたけど、目的は「ジュース」と「お菓子」を買ってもらうこと以外になかった気がするのですが…(~_~;)
ただ子どもの頃の自然体験の積み重ねが今の自分を作っていることは確かで、それと、やっぱり自然との関わりを大切にしている人をたくさん知ってるんですが、みんなお金があろうが無かろうが幸せな生き方してるな~と感じるわけですよ!これホント!
そういう人たちは「自然に感謝」できる人で、そういう人には「幸福感」を感じるセンスが兼ね備わっているような気がします。
私が子どもの遊びに関わったのは、大学で教えられた「人間の幸せの為に都市や街をつくる仕事に携わっているが、当時のまちづくり関連事業では、我々の暮らしはよりよくなりそうに思えない。特に都市に育つ子どもは幸せになりそうもない。」と気付いたことに始まります。
その頃、海外視察で、アレン・オブ・ハートウッドの本「都市の遊び場」に出会ったのです。
自分が子どものころにやったような遊びの写真がいっぱい載った本でした。「子どもの遊びを守るため、世界中いろんな所で、行政施策として取組んでいる」という事実に驚きました。
いきさつがあり、女房とそれを翻訳して出版することになり、その後、2人で本に載っている遊び場を視察に出かけました。当時、女房は2人目の子どもを育てながら家で仕事ができるようにしたいなんて考えていた。
視察から戻って、「じっとしていられない。自分の子どもはすぐ大きくなってしまう。自分たちで遊び場を作る仕事を始めなきゃいけない。翻訳して普及を待つなんていう、まどろっこしいことじゃ駄目だ」ということになったのです。
1975年に世田谷経堂の家から300メートルの緑道予定地の空地を夏休みだけ借りて、遊び場の運営を始めた。
子どもたちの投票で「こども天国」と名付けられた遊び場で、近所の人たちや学生ボランティアと協力して始めたのが最初です。それがやがて「夏休みだけじゃあ子どもに申し訳ない」ということになった。最初の年、7~9月と3カ月やって止めようとしたとき、子どもたちから「何で止めるんだ」と反対された。
区からは3カ月間の約束で土地を借りていたので、返さないと住民はわがままだって、行政に信用されなくなってしまう。何とか返さなきゃいけない、というのが当時の私たちの気持ちでした。
子どもに説得するんだけど、「こんないい所ができたのに、なんで返しちゃうんだ?」というのは子どもの意見でした。すったもんだの末、自分で作った小屋に泊まったり、星空を見たり、名残を惜しんで、「来年もまたやる」約束で取り壊しに応じてもらった。
夏休みが終わってから1カ月かけてつくったものを壊し、捨てるものを捨て、燃やせるものは燃やした。それが、その後こんなに長い間続くとは、私も思っていませんでした。
最初は子どものためなんて言っていたけれど、市民が行動し、社会を変える仕事の面白さにみんな目覚めてしまった。翌年になったら、その時手伝ってくれたお父さんが「これで飯が食えるんなら俺、こっちの方やるね」なんて言ってました。でも残念ながら飯は食えないわけで、いつの間にか飯のための都市デザインの仕事と、家庭の仕事としての遊び場の両方やる羽目になったわけです。
自分たちで我が子、或いは地域の為に行動する楽しさに、私はその時初めて気付きました。世田谷区長と交渉したり、公園課長さんの理解を得ようとする努力など煩わしい仕事を通して、考えていたことがひとつ実現した時の快感は得も言われぬものです。そんなことの連続で、少しずつ遊び場の仲間が増えました。そして、あっという間に30何年経ち、みなさんと子どもの遊びに関わっている。
こうした地道な地域活動が、社会の中で力を持つことの重要性は、実は都市デザインの仕事でも同じです。
住民運動は当時からあったわけですが、主として反対運動でした。
そんな所で仕事をしていて、住民が「こういうことをやりたい。こういうふうにしたい。」という意見が先ずあって、それを実現するにはどうしたらいいか。反対するんじゃなくて、市民の積極的な意見が出て、それを住民も汗かきながら実現していくような動きが起きて欲しいと思っていたのです。
「子どもの遊び場がない。次第になくなるぞ。」と言っても、「困ったなぁ」といって行政にお願いするだけじゃなくて、「自分たちで手を動かし、汗かいて何かやろう」って人たちが出てくることを、当時、飯を食う方の仕事では痛感していたんです。そういう意味で「他人事にせずに、自ら汗をかこう」というのが、女房たちと遊び場づくりを始めた当時の気持ちでした。
ところが、やっている間に世田谷区が理解を示しだし、「羽根木プレーパークを一緒につくろう」という話になってきた。
しかし当時は、いろんな条件が整ってないもんだから、プレーリーダーの天野さん天野秀昭は悪戦苦闘でした。条件がちゃんと整っているところでやるのは楽だけれど、条件の整ってない中で、それを整えつつ事業をするのが、我々のやらなければいけない仕事だと思っていました。
そういう意味で、プレーリーダーは、いわゆる学校の先生などのような安定した給料が貰えない。そしてある年齢になると、家族を支える為に、プレーリーダーはやっていけなくなる。若い人がプレーリーダーであること自体はいいと思うんですが、そのうち何人かは歳とってもプレーリーダーとして後輩を指導するようにならないと、職域として確立しないと思うんです。
プレーパークが社会的に位置づくために、彼らにちゃんとした給料の出る仕組みを作らないといけないと思っています。
今あるかたちが冒険遊び場の全体像ではないと思います。
我々がやるべきことは、生まれてくる次の世代が生き生きとした人間に育ち、人間を元気にし、世界がそれによって活性化するような、人間・社会人を育てることにあると思います。
今日の我々が取り組んでいる「子どもを信じ、子どもが自由に主体的に行動できる環境をつくること」が重要だと思っています。
そういう意味でこの5回目の全国集会の流れが全国に散らばって、それぞれの地域の子どもの環境をつくる運動に繋がるといいと思っています。
当時は、まちづくりに関連して、老人の為のいろいろな施設、施策、予算が手厚くなってきた時期です。高齢化社会になり、老人の声が大きくなった一方、子どもは発言することがない。子どもは納税者ではないこともありますが、保護者の社会性にも問題があって、子どもの施策はなかなか進まない。しかも子どもは減っている。
私は一応都市計画専攻なので、この割合でどんどん減ると、少子化社会で地域の接続が大問題になると見当は付く。間もなく子どもが少なくなって困る時期が来ると思っていました。
羽根木プレーパークを始めた30年前、まだ高齢者の施策重視社会だったけれども、次の世代の子どもの為に、子どもの予算をもっとつけなきゃいけない時代が来ると思ってたんですが、30何年経っても未だ、子育てに対するいろいろな発言などが出るようになったから前よりましかもしれないが、まだ足りない。
次の時代を担う人たちにどんな力を持ってもらうか。また育つ過程でどれだけ楽しい思いをし、自分で仕事をやる自信を持てるかということが重要だと思うんです。
野球の選手などは、イチロー選手みたいに家庭でしっかり教え込むと、若くして、驚くようなお金を稼ぐ人が出てくるわけです。いろんなジャンルで子どもたちが自分のやることを見つけ、それに喜びと自信を持って取り組める仕組みを作ることが大切だと思っています。
そういうもの、スポーツや音楽や最近の芸能界ばかりじゃなく、科学的な分野だとか、もっと日常的な商業の分野だとか、いろんなところで自分の能力を見つけて、生きて、社会がその人の行動によってより良くなるようなこと、人に喜ばれることをベースに生きる人たちがどれだけ出てくるかがとても重要だと思っています。
そのために「遊び」が果たす役割が大変大きいのではないかと思っています。自分の好きなことを自分の好きなペースでやって、そのなかで「やった!」という思いを体験し、失敗にめげず、また新たにチャレンジしようとする姿勢は、日々やっていることのなかで快感を味わい、それを繰り返す体験がとても重要です。
主体的に行動することによって自分の好きなことを見出し、喜んで何度も繰り返して実力をつける体験を、子どもの時にぜひ味あわせたいものです。
特に重要なのは5歳以下の時期です。5歳以下のときに見知らぬ人と、自分の力で交渉する体験が大切だと思います。
最近は子どもが少なくなりましたが、昔は兄弟が3、4人いて、よく兄弟喧嘩があった。自分の意のままにならないということがいっぱい起きる。兄だけが良い目を見ていると不満な弟の思いがあり、兄弟喧嘩が起きる。外に遊びに出ても、砂場に置いてあったバケツをめぐって子どもの取り合いが起きる。そんなとき、どう対処するのかは、親がいれば「あなたは大きいんだから貸してあげなさい」なんてジャッジしてしまうわけですが、本当は引っ張ったり、引っ張られたりしながら、どう対処するのがいいかを体得するのが、多分、コミュニケーション力の発達に大事な教育方法だろうと思うんです。
そういう体験が少なくなって、子ども時代に、親は関係なく、自分の意思で他人と遊んだり話したり、或いは喧嘩したりする体験が少なくなっています。
そのまま大人になって、ある日突然、昔はいい子だった筈の人が、人を刺してしまったりする事件を起こす。そうなる前に、上手く話を付け、自分の意見を通し、自分の思いを実現していく方法を知ることが大切だと思います。
ITは進むのに、コミュニケーション力のない大人が増えた社会は、文化をつくる力の弱い社会をもたらすおそれがあります。「遊び」の力を盛りたてて、子どもたちが自ら自分を育てるチャンスを、出来るだけたくさんつくっていく必要があるのではないかと思います。
※大村 虔一 (おおむら・けんいち)
昭和13年、仙台生まれ。 日本の都市計画家, プランナー・アーバンデザイナー・建築家。教育者。東北大学名誉教授。元宮城大学副学長。羽根木プレイパーク実行委員会初代会長でプレーパークを日本に紹介し作った、プレーパークの生みの親としても知られる。
インストールされたプログラムに働きかける
自分の子どもは長女が4歳、次女が1歳です。
長女の幼稚園は、禁止事項がなく、みんなで一斉にこれして遊びましょということもなくて、お絵かきしたい子はお絵かき、外で遊びたい子は外遊びをするというところです。喧嘩とかはありますが、余程のことがないと大人は介入しないです。興味深いのは、そういう幼稚園に耐えられない子どもはいないけど、親が結構いるということです。誰々が突き飛ばしたのに、園が管理しなかったとクレームを付け、最終的に辞めていきます。
子どもの遊び場とか育て方の問題は、多くの場合、実は親の問題だとわかりました。
みんなで一斉に何かをさせるのは、子どもに負担が少ない分、自己決定の力、変化を作りだす力、友だちの輪に入る力が培われず、単に協調的に振る舞う力ばかり養成されることになりがちです。問題にすべきは、「何を最終的に評価するべきか」ということ。子どもがその時辛くても、将来立派な大人になるために必要な条件を培っているという考え方をどこまで貫徹するかが重要なポイントとしてあります。
マイケル・サンデル※(1)の白熱教室で「トロッコ問題※(2)」は有名です。サンデルがこの問題を出す理由は簡単。身体的な近さ遠さが、感受性の働き方を決めてしまうということを言っています。どうして習得性では説明できない巨大な偏差がプログラミングされているかというと、恐らく何百年、何千万年、共同生活をしてきたことと関係があるんだろうということです。
子どもに森を歩く経験はさせたいと、山荘に連れて行くんですね。森で虫や動物に会うとか、夕方だんだん暗くなって、木のざわざわいう音がしてくるとか。そういう森の環境を子どもがどう受け止めているのか、つぶさに観察をすると、絶対他では得られないような経験をしていると確信できるんです。
この夏、子どもと栗拾いをしたんですね。日が暮れて暗くなると、森の存在感が大きくなるのが子どもにもわかる。そういう変化をもちろん恐がりますし、不安がるけれど、この経験のビフォアーとアフターで子どもの振る舞いが随分変わることに気づきます。
それは単に幼稚園で「みんな栗拾いをしたことがないでしょうから先生が栗を見せます」とイガ付きの栗を見せると、子どもは見たことあるから「そんなもんは全部知ってるもんね~」みたいになっちゃう話とはちょっと違う「何か」なんですね。
僕たちは、単に人間は学習的な動物だから、何を学習させるかでどうとでもなるって思いがちでしたがどうもそうではない。我々の中にはインストールされた情動※(3)のプログラムがある。これを前提にしてしか、学習の結果得られる新たなプログラムも存在しないことが分かってきたんです。なので、子どもに元々インストールされているはずのプログラムに、どれだけ適切に働き掛けるのかが大事だと思いますね。
設置者責任を問うことが一般化
僕は、昭和30年代、京都で主に育っているんです。当時は運河があって、よく子どもが落ちて死んでました。工事現場の築山とかあると子どもが穴を掘り、秘密基地を作って崩れて、子どもが埋まって死んでました。スズメバチの巣にちょっかい出して、2回刺されて死んでる奴、時々いました。箱ブランコの板と地面の間に足を挟まれて複雑骨折してる奴がいましたよね。それが幼少期の環境でしたが、「設置者は何をしてるんだ」「行政は何をやってるんだ」というコミュニケーションがなかったですね。じゃあ、当時の大人はどう振る舞ったかというと、単純で「だから危ねぇって言ってたろ」。
今これが全部逆になってますよね。運河が剥き出しっていうことはなくて、暗渠化されてるか、柵が作られているか、道は全てガードレールが作られ、校庭は放課後出入り禁止。箱ブランコは日本全国、全面禁止になりましたね。少し前までは、新聞に「何故日本では、運河に柵を付けるのか」「危ないものに蓋をするんじゃなく、そこは落ちたら危ないんだって、実際落ちる奴が時々出ていいんじゃないか」みたいなことが載ってた。
1979年、奈良県で、「隣人訴訟」が起こります。隣の家に預けた子どもが近くの池に入って死んじゃう。それで隣人を訴えた。1983年に出た判決では、隣人に責任はほとんどない、行政や池の管理者にも責任はほとんどない、基本的に子どもの監督責任は親自身にあるという判決だった。ところがそれを転機に、日本はいわゆる「法化社会」に向います。何かというと、この訴訟のように隣人を訴える、設置者責任を問うことが、一般的になってきます。
日本社会の特殊な世論が、このようにさせたんですね。「子どもが危険な目に会うかもしれないのに、それを放置している行政は何なんだ」という発想って完全にクレージーだって了解する人が少ないんですね。
自分たちも危険な目に会っています。スズメバチの巣を突いて蜂が出たらバットで打つとかってやってましたよ。柵のない底なし沼に弟が嵌って、一生懸命、棒を探してきて引っ張って出したこともあります。そういう経験の中で、ある種の感覚を養っていく。「人は簡単に死なない」ってことや、逆に「簡単に死ぬ」ってことであったり。あるいは喧嘩をしても、あることを一緒にして遊ぶと、いつの間にか仲直りができていることも経験する。
僕たちは、自分たちがどう育ってきたのかを忘れた状態で、子どもが危険な目に遭うこと自体がいけないって思いこむことがあったようです。恐らく、危険な目に遭うとか、名状しがたいものに出会うとかで起動するプログラムが僕らの中にあるんですね。そういう恐いもの、名状しがたいものを経験するチャンスは、すごく重要なんだなと思います。
ルドルフ・シュタイナー※(4)は「多くの人は、子どもに早く時計を読ませようとか、字を読ませようとかする。しかし、早く習得させようとしていることの大半は、いつでも取り返しがつくどうでもいいものだ」と言い、「クリティカルエイジ=臨界年齢」という斬新な考え方を出します。
「その時までに習得しておかないと、取り返しがつかない何事か」ということです。
シュタイナーによると、何が取り返し付かないかというと、喜怒哀楽。世界の深さを理解出来る力。これは非常にクリティカルエイジが早いというわけです。何も規制を加えない子どもに絵を描かせると、何がどういう順番で付け加えていくのか興味深いです。僕も全部子どもの作品を写真に撮って分析してます。いつ、いわゆる「頭足人」から胴体が生じたかとか、いつ手足に指が付くようになったかとか。4歳に入った瞬間に手足に指が付くようになりました。誰も何も教えていないのに、いろんなところに自分の感受性が開かれていくのがわかって、面白いですよね。
クリティカルエイジという発想は、取り返しの付くうちに、のちに程なく取り返しがつかなくなってしまう経験を与えることが大事だという考えです。そういう意味で「危険」についての免疫は、恐らくかなり早い時期に「恐さ」や「得体の知れなさ」というのを経験していないと駄目なんだろうと思うんですね。
子どもたちを危険な目に遭わせないとか、とりあえず集団行動をさせて、個人的な選択で人間関係をステアリング(舵取り)するチャンスを与えないとか。大人が良かれと思ってする子どもの負担軽減策の多くが、実は子どもに潜在的に備わっているのか、よく考えてみようと。人が近くに寄ってくれば、何か引き金が引かれる。森にいると引き金を引かれ、水に直面すると引き金が引かれ、蛇を見ると引き金が引かれる。
それは神経生物学的にインストールされていた何かが働いている可能性が高い。それを無視した制度を作る。それを無視した文化を尊重する。そうしたものが基本的に、間違っているんじゃないかってことですね。
1994年、アムネスティ・レクチャーズ※(4)に参加した、リチャード・ローティ※(5)という人が面白いことを言ってるんです。
「我々のアメリカ社会は、1965年まで黒人を人間だとは認めてこなかった。それ以降も女性については半端な人間としてしか認めて来なかった」と。だから原理原則を説いて聞かせることなんかどうでもいい。誰を仲間だと思えるのかって感受性の幅を広げる。それが圧倒的に重要なことなんだって言っている。
この議論は、今日僕がお話していることにとても関係をしています。臨界期という考え方も同じです。実際にだれを仲間だと思えるのかってことは、言葉では決着できない。だからある育ち方をすれば、黒人を差別することも女を差別することもできなくなる。それが人間というものなんだ、ということです。
ですから、実は、子どもにとってどういう遊び場が良いかということは、子どもが何を喜ぶのかということとは、大きく別の問題だと考えざるを得ない。子どもが恐いと思うものや恐ろしいと思うものを塞ぐ。子どもが喜ぶものを与える。完全にナンセンスですよね。そうじゃない。
神経生物学が示唆するところ、サンデルがあるいはローティ―が示唆するところ、あるいは僕自身の経験、皆さんの経験が示唆するところはそれとは全く違う。
介入せずに任せることで解決
子どもは、どうとでも育ちます。だったら、どうとでも育てていいかっていうと、どうもそういうことではなくなってきた。
子どもに仕組まれている潜在性は、親や親族からの遺伝というだけじゃなく、種族的な遺伝的要素があるとわかってきた。それがわかってきた中で見ると、今の日本のとにかく「危険とあらば全て覆い隠す」とか、子どもが喧嘩していれば「介入しなかった」と幼稚園が責任を問われるとか、ナンセンスの極みですよね。今自分の子どもは辛い状況にいるなぁって思ってたら、余程意識していない限り、介入したくなりますよね。でも、介入しないで、ある種の子どもたちの力に任せることで、多くの場合子どもたちが成長し、問題を解決してるんですよね。
昔の人は村のしきたりとか、共同体の作法で、子どもが泣いていても甘やかしちゃ駄目だって、親の自然感情を、社会的な絆で抑止していたんですね。
今、我々大人の側が、共同体の空洞化によって、そういう絆を失っているが故に、自分の自然感情のままに子どもを育てるっていうことが当たり前になってしまった。
80年前後から法化社会が進み、何かというと設置者責任を問うような振舞いが出てきた原因は、やっぱり共同体が空洞化したからですよね。子どもにそれは危険だと教えるのが大人の務めで、危険を塞ぐことが務めじゃないって、昔の人間だったら言ったはずなんですが。
所詮、人間は弱いから法化社会を進めるような存在は、共同体の絆が薄れていけば必ず出てきます。ではその人間たちに対して、僕たちがどうやって坑っていくのか。僕たちはむしろ今、少数なんです。1979年は、10人いれば1人いるのがこういうのを進める奴らでしょうけど、今は10人いれば9人が設置者責任の追及者かもしれない。
そういう中で、子どもの持っている潜在性を存分に生かすために、危険な目に遭わせる、トラブルを自分で克服させると考える親が少ない。だったらその人間たちは連携をして、自分たちの方が間違っていないんだと、実績によって証明していくしかないんです。
世の中そんなもんだよね
僕が子どもをどういうふうに育てるか。「嘘をついちゃいけないよ」「悪をしちゃいけないよ」とか普通言うでしょ。うちは違うんですよ。「嘘をついちゃいけないよ、でも、ちょっとはいいよ」「いろんな悪い奴が確かにいるんだよ。いじわるな奴もいる。でもね、世の中そんなもんなんだぜ」って言いますね。すると、うちの娘は3歳半ぐらいから「世の中そんなもんだよね」って言うようになったんですよね。
今、いろんな工夫をしないと、日本でお仕着せのルールに思考停止的に従うことから逃れられないんだろうなって思います。
皆さん、ルールに従いなさいって教えてるでしょうか。それは馬鹿げている。日本では特にそれは教えない方がいい。「ルールには従った方がいいけど、ちょっとぐらい破ってもいいよ」そうすると「ちょっとぐらい破ってもいいというのはどういうことなのか」って考えるじゃないですか。「どういうときに破ったらいいのかなぁ」って。これはすごい大事だと思うんですね。
いろんなものがいい加減なんです。世の中。何が人間かもいい加減だし、何が日本かもいい加減。いい加減なものがあたかも杓子定規であるかのように思い込まされているだけで、実際現場に行ってみれば、何にもそこに一貫したルールがないってことがよくわかる。まぁそんなもんです世の中。だから仮の姿で社会を生きていく、そういうふうな子どもに育てなきゃ駄目だと思うんです。
僕はこのようなNPOに関わって、社会の中の少数者としての生き方を選択することは賢明だと思うけど、それがある種、純化主義みたいになると、子どもがその中でしか生きられなくなってしまうので、世の中がどう回ってるのかということも、やっぱり同時に教える必要があると思っています。「君は恐がりじゃなかった。でも、周りは恐がりだ。その時に『恐がり恐がり~』って言ったらいじめられちゃうからね。『恐いのもわかるよ~』って言うんだよ」って教えるって大事ですよね。
ということで、僕の今日の話のまとめとして、遊び場に限らず、子どもたちが元々持っている潜在性を生かしながら、しかしこの社会を生きて行くときに、過剰な違和感を抱かなくて済むように、この社会の成り立ちを含めて学んでいく、また学ばせていくことが大事なんだというふうに思っています。
※宮台 真司(みやだい しんじ)
1959年3月3日 、仙台生まれ。日本の社会学者、映画評論家、学位は社会学博士(東京大学・1987年)。首都大学東京教授。
援助交際、ブルセラなど若者のサブカルチャを弁護してきた稀代の論客として、カリスマ的な存在である。著書には「日本の難点」「14歳からの社会学」「<世界>はそもそもデタラメである」など多数。
| マイケル・サンデル※(1) アメリカ合衆国の哲学者、政治哲学者、倫理学者。ハーバード大学教授。コミュニタリアニズム(共同体主義)の代表的論者であり、その論述の特徴は共通善を強調する点にある。サンデルの「政治哲学」講義を収録したテレビ番組「ハーバード白熱教室」 (Justice with Michael Ssndel)が有名である。 |
| トロッコ問題※(2) 「ある人を助けるために他の人を犠牲にするのは許されるか?」という倫理学の思考実験。フィリッパ・フットが提起し、ジュディス・ジャーヴィス・トムソン 、ピーター・アンガーなどが考察を行った。人間がどのように道徳的ジレンマを解決するかの手がかりとなると考えられており、道徳心理学、神経倫理学では重要な論題として扱われている |
| 情動の発達※(3) ブリッジスK.M.B.Bridges(1897―?) 新生児の情動は興奮だけであるが、そこから快と不快の2方向が分化し、さらに快から得意、大人に対する愛情や喜びが分化する。また不快からは怒り、嫌悪、恐怖、嫉妬が分化する。そして、2歳ごろまでには人間としての基本的な情動が出そろう。なお、幼児期になると、羨望、失望、不安、羞恥、希望などの情動も発現し、5 歳ごろまでには大人にみられる情動のほとんどが出そろってくる。(日本大百科全書より) |
| ルドルフ・シュタイナー※(4) Rudolf Steiner,(1861-1925) オーストリア帝国(1867年にはオーストリア・ハンガリー帝国に、現在のクロアチア)出身の神秘思想家 。アントロポゾフィー(人智学)の創始者。哲学博士。また教育、芸術、医学、農業、建築など、多方面に渡って語った内容は、弟子や賛同者たちにより様々に展開され、実践された。中でも教育の分野において、ヴァルドルフ教育学およびヴァルドルフ学校(シュタイナー学校)が特に世界で展開され、日本でも、世界のヴァルドルフ学校の教員養成で学んだ者を中心にして、彼の教育思想を広める活動を行っている。 |
| アムネスティ・レクチャーズ※(4) オックスフォード大学で行われる、アムネスティ・インターナショナル(和名「国際人権救護機構」)主催の講演会。 |
| リチャード・ローティ※(5) Richard Rorty (1931- 2007) アメリカ合衆国の哲学者。スタンフォード大学で哲学や比較文学の教鞭をとった。プラグマティズム(実際主義)の立場から近代哲学の再検討を通じて「哲学の終焉」を論じた。また、哲学のみならず、政治学、経済学、社会学、アメリカ文化などの論壇で活躍。現代アメリカを代表する哲学者である。プラグマテイズムの代表者ジョン・デューイや、トーマス・クーン、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインらの影響を受ける。 |